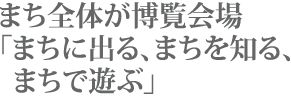| ホーム > 金沢散歩学 > 東山山麓の地蔵巡り |
||||||||||||||||||
東山山麓の地蔵巡り |
||||||||||||||||||
浄土宗。越前府中より前田利家の金沢入城に従って新丸の中に寺地を拝領、現在地へは寛永13年(1636)に移転。江戸時代中期に作られた山畔池泉式の庭がある。
浄土宗。京都清浄華院35世心蓮社休誉(能登の長連龍の弟)が慶長17年(1612)、塩屋町に創建。寛永14年(1637)現在地に移る。寺宝の国重文阿弥陀三尊来迎図は、わが子が夫に殺されたという誤報を聞いて失明した女性が、この阿弥陀仏にすがって視力を取り戻したと伝えられ、「目明きの阿弥陀」とも呼ばれる。
日蓮宗。慶長19年(1614)越中富山妙国寺の住僧日全を開山とする。本寺の鎮守に大黒堂があり、日蓮上人作と伝えられている大黒天像を安置している。 また庭園には、玉木大明神という蛇の霊を祀る石作りの祠堂がある。木像で、それには「大鬼女菩薩、文化三年寅十月、十一代孝寿院日亀勧請」と記されている。
来迎山と号する浄土宗寺院。地蔵堂は境内にあり、現在のものは昭和30年に再建されたものである。以前は浅野川地区の弁天信仰の中心的寺院でもあった。 (1)延命地蔵尊 右手に錫杖、左手に宝珠を持つ。毎年8月24日には寺による地蔵供養のお勤めがある。当時は「誠心堂」という地蔵講があったが、現在、その機能は衰退している。お堂は昭和30年に再建されたもの。
天台宗寺院。当初は越前府中にあったが、慶長17年(1612)前田利長より、現在地を賜わり、諸堂を再興して、加越能天台宗の触頭を拝命した。 (1)身替り地蔵尊 お堂の中の地蔵尊は20体、2体の観世音を合祀。板碑式の観音立像の背面に「元禄十六年」の文字が見える。
この辺り、藩政時代、歩組の佐賀関助が再興した開助馬場の北側土居跡と平行していた道であり、後に染物、(金)箔打ち、建具職人、大工などが住む職人町となっていたところであった。 地蔵尊の縁起は明確でないが、現在の場所には明治初期よりの小さい寺があったが、老朽化したことで、暗和15年にここにお堂を建てた。奉賛は延命地蔵尊奉賛会。 毎日のお世話は奉賛会と町内会で行い、毎月の地蔵さんのご縁日を24日、水子供養の日として6日と決めてお祀りしている。 また毎年8月24日には近隣の人々が集まり、僧侶が招かれて盛大に地蔵まつりが行なわれている。参加地域は、昌永町、東山3丁目、森山2丁目。お供え物は子供たちに与えられる。祭りは午前9時より午後10時頃まで。 地蔵尊のご利益は (1)地蔵にお参りすると、達者で長生きする。 (2)お堂の中の弁財天は、学問上達と商売繁盛。毎月12日は弁財天の日。 ※近くには、明治の初めより第二次大戦ごろまでつづいたという芝居小屋「戎座」があった場所がある。
|