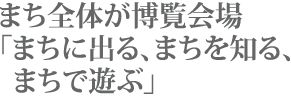| ホーム > 金沢散歩学 > 犀川筋の地蔵尊を巡る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犀川筋の地蔵尊を巡る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 潤光山と号し真言宗に属する。平安時代天長元年(824)、淳和天皇の勅命により、大聖歓喜天を勧進して創建されました。元禄6年(1694)、当院の住僧隆元阿閻梨は吼桜明神の霊告により、弘法大師作の地蔵菩薩をお迎えし、当院のご本尊といたしました。寿永2年(1183)6月、兵火にかかり再建されました。正保3年(1646)元佑上人によりまた再興されました。正徳年間(1711〜1715)、五代藩主綱紀公は、この辺りの寺院にことごとく転置を命じましたが、綱紀公の夢枕に地蔵菩薩が現れて「養智院は鬼川の守護のため永く残し置かるべし、我れ必ずこの用水を守護すべし」と誓って姿を消されました。このため養智院は、外堀を兼ねた鬼川と金沢城の裏鬼門の守護のために、この地に残されました。
潤光山と号し真言宗に属する。平安時代天長元年(824)、淳和天皇の勅命により、大聖歓喜天を勧進して創建されました。元禄6年(1694)、当院の住僧隆元阿閻梨は吼桜明神の霊告により、弘法大師作の地蔵菩薩をお迎えし、当院のご本尊といたしました。寿永2年(1183)6月、兵火にかかり再建されました。正保3年(1646)元佑上人によりまた再興されました。正徳年間(1711〜1715)、五代藩主綱紀公は、この辺りの寺院にことごとく転置を命じましたが、綱紀公の夢枕に地蔵菩薩が現れて「養智院は鬼川の守護のため永く残し置かるべし、我れ必ずこの用水を守護すべし」と誓って姿を消されました。このため養智院は、外堀を兼ねた鬼川と金沢城の裏鬼門の守護のために、この地に残されました。昭和28年、都市計画により多くの境内地を失い往時の静寂さは偲びがたいけれども、霊験あらたかな地蔵菩薩と大聖歓喜天(天部)霊場として、今なお隆盛を極めています。 本尊地蔵菩薩 当院の本尊地蔵菩薩は加賀延命地蔵尊といわれ、平安時代の天長2年(825)弘法大師が北国を巡錫〈じゅんじゃく)された時、能登の国、吼桜山に登り霊木を彫刻されました。地蔵尊は丈(2尺5寸)の立像で渚願成就の菩薩さまとして市民に大変親しまれています。また、文学の地蔵ともいわれ、和歌などにもうたわれています。 鬼川延命地蔵尊 徳道上人の地蔵 右手に錫杖、左手に金剛鈴(数珠)を持っている。 笏谷石 赤戸室石の地蔵 合掌している 延命地蔵 右手に錫杖、左手に宝珠 青戸室石
 旧金沢宝船路町にあって、仏海山と号し、浄土宗に属する。
旧金沢宝船路町にあって、仏海山と号し、浄土宗に属する。当寺ははじめ、尾張の国・犬山にあったが、開山念誉一公上人は加賀初代藩主前田利家公および二代藩主利長公に従い、越前府中(武生市)越中守山(高岡市)、富山と移った。慶長4年(1599)利長の金沢移城に伴い、現在の犀川橋詰めに旧地に寺地を拝領した。五枚町から古寺に入る角の所である。 当寺の二世近誉深公上人の母堂は利長公の乳母にあたる。寛永8年(1631)大火に見まわれ、いったん地所を返上したが、元禄14年(1701)第九世・正誉覚弁上人が再び当所において現在の堂を建立した。 法船寺は、江戸時代から地蔵信仰霊場巡りの一つとなつていた。そのお地蔵さまは今は山門の陰に置きやられた状態になっている。地蔵祭りは戦後行われず、お盆にはこの寺の境内で盆踊りが盛大に行なわれていたという。 その後、法報会の会員、その他により新しいお地蔵さまが境内に安置されるようになり、法報会の提唱により地蔵祭りが行なわれるようになりました。 地蔵尊像-1 寺本来のお地蔵さまはあるが、法船寺のお地蔵さまと呼ばれるだけで、固有の名前はない。 右手に錫杖、左手に宝珠を持つ地蔵。 鶏亀地蔵(地獄道)立像(約2m)笏谷石 安置年代は不明であるが江戸時代 地蔵尊-2 花崗岩の地蔵(笠付角柱形〉 墓石に彫刻したタイプ(大蓮寺にもあり) 右手に錫杖、左手に宝珠を持っている。
 地蔵堂の中央にあるのが歯痛地蔵尊である。木製の立像で、手に宝珠を持っている。江戸時代に、虫歯と頭痛に苦しんでいた国泰寺の志謙禅師が、同じ苦しみを持つ衆生(生きているすべてのもの)を救おうと、持仏を彫刻して、自分の歯を3本抜き取って地蔵の頭に納め、歯痛と頭痛の平癒を願ったという。左手にあるのは延命地蔵尊で、延命長寿・子孫繁栄のために武蔵の国で作られたものだが、三代藩主利常公の夢枕にこの地蔵が立ち、加賀に移すようにと告げたので、家来に命じて国泰寺に寄進したという。
地蔵堂の中央にあるのが歯痛地蔵尊である。木製の立像で、手に宝珠を持っている。江戸時代に、虫歯と頭痛に苦しんでいた国泰寺の志謙禅師が、同じ苦しみを持つ衆生(生きているすべてのもの)を救おうと、持仏を彫刻して、自分の歯を3本抜き取って地蔵の頭に納め、歯痛と頭痛の平癒を願ったという。左手にあるのは延命地蔵尊で、延命長寿・子孫繁栄のために武蔵の国で作られたものだが、三代藩主利常公の夢枕にこの地蔵が立ち、加賀に移すようにと告げたので、家来に命じて国泰寺に寄進したという。この地蔵は「火の用心のために夜回り」をされたという伝えがある。 右手の地蔵尊は、水難除けの地蔵である。昔、犀川の川下で拾われ、一切の水難から救つてもらうことを祈念して安置されたという。 地蔵尊像 堂内には大小18体の地蔵が安置されている。 歯痛地蔵尊 中央にある地蔵 木製の地蔵(高さ62cm)手に宝珠を持っている 安置年代 江戸時代 延命地蔵尊-左手にある 武蔵の国で作られ延命長寿、子孫繁栄、疫病災難除を祈願して作られた。 右手に錫杖、左手に宝珠を持っている。 水難除地蔵尊 右手にある 犀川の川下で拾い上げられた地蔵 右手に錫杖、左手は宝珠か
金沢市千日町にあって、高野山真言宗に属する。 千日山とも福智山とも称する。 雨宝院が建立された文禄4年(1596)頃からのものと伝えられている。雨宝院は地蔵菩薩順拝二十四カ所の第二十二番日の順拝所であった。 子安地蔵尊 子安地蔵尊は彩色されたあとがある。唇は赤く塗られており女性的である。地蔵尊の胸のあたりに衣のひだの上に赤ん坊がおり、子安地蔵尊の胸のあたりまでさがつている数珠に手をのばしてつかんでいる形に彫られている。 子供は首より上の部分は離れているが、下半身は地蔵尊とつながっている。 延命地蔵菩薩-十輪堂 雨宝院十輪堂内の延命地蔵菩薩は、犀川巡礼二十四カ所の一番寺であった遍照寺のお地蔵さまである。 明治22年に寺号を廃した折、雨宝院に移された地蔵菩薩の一つである。弘法大師の真作と伝えられているこの地蔵菩薩は、木製の立像で、右手に錫杖、左手に宝珠を持ち、台座を入れた総高は105cm、頭部から足までは83cm、頭首長13cm,面幅10cm、側面最厚幅15cm、台座(蓮華座)は蓮の花びらを集めたような形になっており、高さ14cm、幅30cmである。頭巾はなく、よだれ掛けだけである。 雨宝院前の六地蔵
1)常夜燈(赤戸室石) 献燈・御神燈・奉納・奉寄進 製作年代 弘化三年(1846) 文久元年(1861)五月吉日 2〉狛犬(二基) 昭和九年(現在の天皇御誕生記念)
金沢市野町二丁目にあって、宝池山と号し、浄土宗に属する寺である。 延命地蔵尊 秘仏化されていて、地蔵堂のお厨子は45年程開かれていない。 隕石ではないかという説もある。 地蔵尊-2 花崗岩の地蔵 (笠付角柱形)墓石に彫刻したタイブ(法船寺と同じタイプ) 右手に錫杖、左手に宝珠を持っている。
金沢市野町(旧蛤坂町)にあって、安養山と号し、浄土宗に属する。 山門の右側に地蔵尊が18体ある。 水子地蔵 9体 子安延命地蔵 5体 舟形光背、浮彫りの立像地蔵1体 凝灰岩製 1.1m 未敷蓮華を持つ立像の地蔵-笏谷石製 半跏像の地蔵 右手に錫杖、左手に宝珠
金沢市野町(旧蛤坂町)にあって、高養山と号し、浄土宗に属する。 正保四年(1647)、これより前に松平又右衛門が没したとき、子供がいなかったので、その後室が寺を起こし、又右衛門の戒名によって初め成学院といったが、後に成学寺と改めた。 地蔵尊像 総高1.7m、蓮華座に立って合掌している凝灰岩製の石像。
金沢市寺町(旧泉寺町)にあって、恵光山と号し、天台宗に属する。 最初は越前府中にあり、天正十二年(1584)利家の息女菊姫の没した時本寺滋賀の西教寺に葬り、十三年(158・5)当時の盛尊を招いて寺を河原町に建てられた。 元和二年(1616)に今の場所に移った。 地蔵堂のなかには、身代わり地蔵〈凝灰岩・半跏像)・延命地蔵尊(立像・銅製・富山県高岡市の金屋町で鋳造)・飴買い地蔵(凝灰岩・坐像) 身代わり地蔵尊 右手に錫杖、左手に宝珠を持つ半跏像の地蔵 延命地蔵尊 高さは台座を入れて213cm、頭首長は36cm、面幅は30cm、右手に錫杖、左手に宝珠を持ち、台座には蓮華の花が描かれている。 飴買い地蔵尊 高さは台座を入れて100cm、頭首長は25cm、面幅18cm、両膝幅72cm、側面最厚幅20cm、両手で宝珠を持ち、雲の模様のある台座に座っている。
|