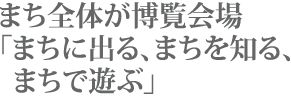文禄元年(1592)、金沢城築城のための巨石を戸室山から引き出す工事の安全を願って建立されたといわれるお地蔵さん。毎年8月に町内の人々によって地蔵祭が行われる。
「珠姫」の寺として有名。珠姫が前田利常(3代藩主)に嫁いで来たのが3歳。利常9歳。2代将軍徳川秀忠の娘。千姫の妹、家光の姉にあたる。江戸からの行列は、わざわざ東海道をまわり90日もかけての豪勢な列だったという。光高(前田家4代藩主)をはじめ、三男五女を産むが、24歳の若さで病死。
小立野に大寺院が作られ葬られる。法名をとって「天徳院」。

天正年間に越中で創建され、のち現在地に移転した。3代藩主利常の妻として迎えられた珠姫が、祖父の徳川家康公の位牌をまつったといわれる。所蔵する絹本着色三尊来迎図(南北朝時代)は市指定の文化財。
日蓮宗で山号を寿福山という。慶長10年(1605)創建。
墓地に、6代藩主吉徳の側室で、加賀騒動に関与したとして幽閉され、43歳で没した真如院の墓がある。
加賀騒動は、のちに芝居や講談で世間に流布された。
菅原天神を祀り、永仁5年(1297)京都北野天満宮より勧請される。前田家が領主となり祈願所とし、当時金浦郷の総社となり、田井天満宮(田井天神)と称した。
椿原天満宮横の天神坂を下ったところが天神町。地内に田井天神があることからこの名がついた。金沢城下町のうち、地子町のひとつ。町家が並ぶ天神町通りはなかなか風情がある。

田井村の農民が小立野台へ馬をひいて草刈りに通った道なので、この名がついた。六曲り坂ともいわれた。坂の途中に目に効くといわれる馬坂不動寺がある。

曹洞宗。前田家藩主一族の位牌が安置された菩提寺であり、墓所内には、利家の自画像と髪を納めた御影堂・御髪堂がある。
前田利家は府中時代(現・福井県越前市)に高瀬村(越前市高瀬)の宝円寺の住持大透圭徐(だいとうけいじょ)に帰依(きえ)し、当寺を外護(げご)再興したといわれる。
利家が天正9年(1581)に能登へ入国後七尾郊外に宝円寺を、大透を開山として招き、天正11年(1583)に、金沢に移封される際に宝円寺を城の東南(金沢市宝町)に建立し、天徳院とともに加賀藩、曹洞宗の触頭となって藩の宗教行政の一翼も担った。大透は、金沢の宝円寺からのちに七尾の宝円寺に退いて、寺号を利家の母の院号をとり長齢寺を建立した。
大透は利家と同じ尾張の出身で、利家に請われる形で、府中、七尾、金沢と居を移した。
 文禄元年(1592)、金沢城築城のための巨石を戸室山から引き出す工事の安全を願って建立されたといわれるお地蔵さん。毎年8月に町内の人々によって地蔵祭が行われる。
文禄元年(1592)、金沢城築城のための巨石を戸室山から引き出す工事の安全を願って建立されたといわれるお地蔵さん。毎年8月に町内の人々によって地蔵祭が行われる。 天正年間に越中で創建され、のち現在地に移転した。3代藩主利常の妻として迎えられた珠姫が、祖父の徳川家康公の位牌をまつったといわれる。所蔵する絹本着色三尊来迎図(南北朝時代)は市指定の文化財。
天正年間に越中で創建され、のち現在地に移転した。3代藩主利常の妻として迎えられた珠姫が、祖父の徳川家康公の位牌をまつったといわれる。所蔵する絹本着色三尊来迎図(南北朝時代)は市指定の文化財。 田井村の農民が小立野台へ馬をひいて草刈りに通った道なので、この名がついた。六曲り坂ともいわれた。坂の途中に目に効くといわれる馬坂不動寺がある。
田井村の農民が小立野台へ馬をひいて草刈りに通った道なので、この名がついた。六曲り坂ともいわれた。坂の途中に目に効くといわれる馬坂不動寺がある。 曹洞宗。前田家藩主一族の位牌が安置された菩提寺であり、墓所内には、利家の自画像と髪を納めた御影堂・御髪堂がある。
曹洞宗。前田家藩主一族の位牌が安置された菩提寺であり、墓所内には、利家の自画像と髪を納めた御影堂・御髪堂がある。