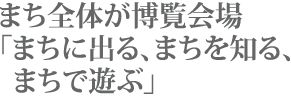下口街道は、北國街道の北へ向かっての道を指し、金沢から富山方面に向かう方向となる、逆に京に上る方は上口街道と謂われていた。
| 2.野蛟神社(ぬづちじんじゃ 金沢市神谷内町へ-1) |
うらやましうき世の北の山桜
芭蕉が元禄5年正月に金沢の門人句空宛に贈った句。
浮世の北とはその金沢を指す。句空が『北の山』を編纂するに際して序文を辞退して代わりに発句を書いて送った。
現存する『句空宛書簡』は断簡でその内容は見えないが、どうやらこの句と、ともかくもならでや雪の枯尾花の2句を与えたようである。
註:(句空=加賀蕉門の人。芭蕉が『奥の細道』で金沢滞在中に門人となる。平民ながら剃髪して、金沢の卯辰山金剛寺近くの柳陰庵に隠棲。句集として『北の山』などがある) |

境内の句碑は宝暦13年(1763)蘭更が芭蕉の70回忌を営んだ折に建立したと伝わるが、「宝暦壬午仲春下浣半下坊」の文字も既に読み取れない。もとは北國街道沿いのサクラの木の下にあったが、(1)昭和30年の道路拡張工事の際に現在地に移転したと謂う。(2)明治初年にこの地に移す。 の2説がある。
句 意:あなたの住んでいる金沢は静かな場所でうらやましい。私は今江戸にあってよろず浮世の問題に悩まされています。「浮世の北」は北国金沢の意。句空は、金沢卯辰山のふもとに住んでいることを芭蕉は知っていたので、句空のことを「山桜」にたとえた。芭蕉はこの頃、長旅の疲れと体調不良、門人達の確執、家族の病弱、住いの狭隘と喧騒など、身辺近くに多くの問題を抱えていた。

村名の由来は昔ここに大きな樋があったことにより、大樋といえば大樋焼きが知られている。加賀の楽焼で宗家は大樋長左衛門である。寛文6年(1666)5代藩主・綱紀の招きで利休の4代目の孫である仙叟に伴って金沢に来たのが長左衛門で、長左衛門は大樋村に居を与えられ、俗に言う「大樋の飴釉」を創案した。藩の御用釜として名字帯刀を許され、士分の待遇を受ける。古くより「一楽、二萩、三唐津」と云われる様に、緑の茶と柔らかな楽の手触りの調和は欠かすことができない。
俗に子安観音ともいい、大樋の産土神で子宝と安産の神である。養老7年(723)の創設と伝えられる。同じ敷地内に乳母嶽銀神社があり、「子授け石」がある。石を摩った手でお腹を撫でれば子宝に恵まれると謂う。
藩政時代には春日町と大樋町の境が町地と郡地の境になっており、ここを下口と言った。参勤交代の列は是より内は行列を整然とし、外では列を乱すことに対して寛大であったと謂う。また、財政の逼迫した時期にはこの地点から外では供の人数も極端に減じたとも伝えられる。
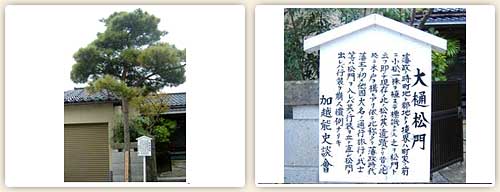
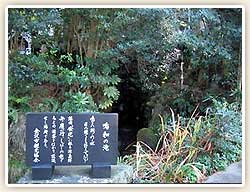
安宅の関を通り過ぎた義経主従は、ここまでくれば一安心と金沢市鳴和の鹿島神社で休憩することにした。そこに安宅の関守富樫泰家がやってきて、地元の酒を差し入れた。富樫の弁慶の知恵と義経の勇気に感服しての行動であった。
その酒で義経らと富樫は宴を開き、弁慶が「これなる山水の、落ちて巌に響くこそ、鳴るは瀧の水」(勧進帳より)と延年の舞を舞った。
弁慶が舞っているそばには見事な滝が流れており、この滝は鳴和の滝と呼ばれ、ここ鳴和町の名前の由来になったと言う。
現在も鳴和の滝は流れてはいるが、残念ながらその滝に当時の面影は見ることはできない。

飴買い伝説が残るお寺。寺院前の飴屋に女性がちょくちょく飴を買いに訪れるので、ある日、不思議に思っ主人が後をつけていくと、お寺の泣く声がするので、その場所を掘ると、墓から元気な赤ん坊が出てきた。母乳の代わりに飴で育てられていたらしい。その子は、後にの墓場に消えていった。不審に思い、翌朝その場所に行くと赤ん坊の泣く声がするので、その場所を掘ると、墓から元気な赤ん坊が出てきた。母乳の代わりに飴で育てられていたらしい。その子は、後に住職に引き取られ、僧侶になったといわれている。
| 8.心蓮社(しんれんしゃ:金沢市山の上町4-11) |
心蓮社休誉が慶長17年(1612)、金沢塩屋町に創建。寛永4年(1637)当地に移る。
阿弥陀三尊来迎図(重要文化財)があるほか、蕉門十哲の一人、立花北枝(たちばなほくし)の墓と句碑がある。
うらやましうき世の北の山桜(芭蕉) 句碑は宝暦12年(1762)俳人・欄更の建立で北陸街道脇にあったが、明治初年ごろ現在地に移された。

写真左:心蓮社 右:立花北枝の墓と句碑
 境内の句碑は宝暦13年(1763)蘭更が芭蕉の70回忌を営んだ折に建立したと伝わるが、「宝暦壬午仲春下浣半下坊」の文字も既に読み取れない。もとは北國街道沿いのサクラの木の下にあったが、(1)昭和30年の道路拡張工事の際に現在地に移転したと謂う。(2)明治初年にこの地に移す。 の2説がある。
境内の句碑は宝暦13年(1763)蘭更が芭蕉の70回忌を営んだ折に建立したと伝わるが、「宝暦壬午仲春下浣半下坊」の文字も既に読み取れない。もとは北國街道沿いのサクラの木の下にあったが、(1)昭和30年の道路拡張工事の際に現在地に移転したと謂う。(2)明治初年にこの地に移す。 の2説がある。 村名の由来は昔ここに大きな樋があったことにより、大樋といえば大樋焼きが知られている。加賀の楽焼で宗家は大樋長左衛門である。寛文6年(1666)5代藩主・綱紀の招きで利休の4代目の孫である仙叟に伴って金沢に来たのが長左衛門で、長左衛門は大樋村に居を与えられ、俗に言う「大樋の飴釉」を創案した。藩の御用釜として名字帯刀を許され、士分の待遇を受ける。古くより「一楽、二萩、三唐津」と云われる様に、緑の茶と柔らかな楽の手触りの調和は欠かすことができない。
村名の由来は昔ここに大きな樋があったことにより、大樋といえば大樋焼きが知られている。加賀の楽焼で宗家は大樋長左衛門である。寛文6年(1666)5代藩主・綱紀の招きで利休の4代目の孫である仙叟に伴って金沢に来たのが長左衛門で、長左衛門は大樋村に居を与えられ、俗に言う「大樋の飴釉」を創案した。藩の御用釜として名字帯刀を許され、士分の待遇を受ける。古くより「一楽、二萩、三唐津」と云われる様に、緑の茶と柔らかな楽の手触りの調和は欠かすことができない。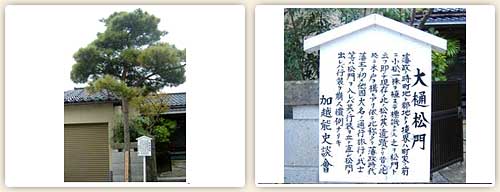
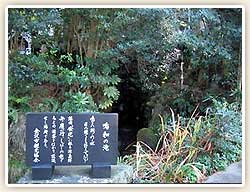 安宅の関を通り過ぎた義経主従は、ここまでくれば一安心と金沢市鳴和の鹿島神社で休憩することにした。そこに安宅の関守富樫泰家がやってきて、地元の酒を差し入れた。富樫の弁慶の知恵と義経の勇気に感服しての行動であった。
安宅の関を通り過ぎた義経主従は、ここまでくれば一安心と金沢市鳴和の鹿島神社で休憩することにした。そこに安宅の関守富樫泰家がやってきて、地元の酒を差し入れた。富樫の弁慶の知恵と義経の勇気に感服しての行動であった。 飴買い伝説が残るお寺。寺院前の飴屋に女性がちょくちょく飴を買いに訪れるので、ある日、不思議に思っ主人が後をつけていくと、お寺の泣く声がするので、その場所を掘ると、墓から元気な赤ん坊が出てきた。母乳の代わりに飴で育てられていたらしい。その子は、後にの墓場に消えていった。不審に思い、翌朝その場所に行くと赤ん坊の泣く声がするので、その場所を掘ると、墓から元気な赤ん坊が出てきた。母乳の代わりに飴で育てられていたらしい。その子は、後に住職に引き取られ、僧侶になったといわれている。
飴買い伝説が残るお寺。寺院前の飴屋に女性がちょくちょく飴を買いに訪れるので、ある日、不思議に思っ主人が後をつけていくと、お寺の泣く声がするので、その場所を掘ると、墓から元気な赤ん坊が出てきた。母乳の代わりに飴で育てられていたらしい。その子は、後にの墓場に消えていった。不審に思い、翌朝その場所に行くと赤ん坊の泣く声がするので、その場所を掘ると、墓から元気な赤ん坊が出てきた。母乳の代わりに飴で育てられていたらしい。その子は、後に住職に引き取られ、僧侶になったといわれている。